物質の三態と熱運動(2) |
|
低温(0 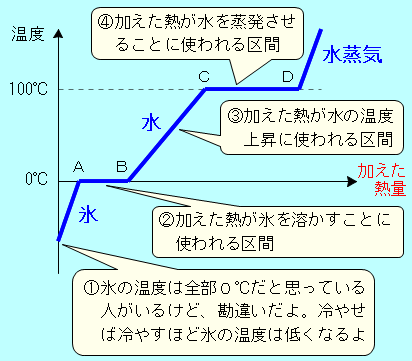 A点で0 AB間は、熱を加え続けているのに温度が上がらないのは、加えた熱(エネルギー)が固体の水分子どうしの結合を切断するために使われているからです。固体を液体にするために必要な熱量を融解熱といいます。 CD間も、熱を加え続けているのに温度が上がらないのは、加えた熱(エネルギー)が液体の水分子どうしの結合を切断するために使われているからです。液体を気体にするために必要な熱量を蒸発熱といいます。 同じ0 また、同じ100 このことから、融解熱や蒸発熱のように、状態を変化させるために使われる熱を潜熱といいます。(潜水艦の潜だよ) 融解熱や蒸発熱は、1gあたりどれくらいの熱量が必要かで表されるので、単位は、J/g(ジュール毎グラム)となります 。
|
||||||||
| → 問題 へ |
||||||||
| |
||||||||