静止摩擦力(2) |
|
前のページのように、引く力の大きさに応じて静止摩擦力が大きくなっていったら、いつまでたっても物体は動きません。 でも、実際は、引く力を大きくしていくと、いつか、あるところで物体は動き始めます。 静止摩擦力には「これ以上大きくならない」という上限があり、これを、「最大摩擦力」といいます。引く力がこれより大きくなると、物体は動き始めることになります。 「これが最大、最大摩擦力」の大きさを、ここでは 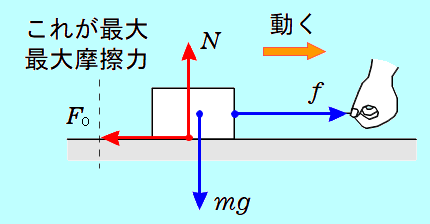 最大摩擦力の大きさ 物体を引いたときに、動き出しやすいか動き出しにくいかは、何が関係するでしょう。
上の (注意:「物体の底面と床面との接触の強さ」は、「物体にはたらく重力の大きさ」ではなく、「垂直抗力の大きさ」です。) 実験によると、最大摩擦力の大きさ となります。 比例定数 上の式から、左辺の 静止摩擦係数 (例)静止摩擦係数のめやす(教科書p77表1、他より)
表の数値から、氷の上や、テフロン加工のフライパンが、すべりやすいことがわかります。 また、例えば、鋼鉄と鋼鉄は鉄道の車輪とレールを、コンクリートとゴムは道路とタイヤをイメージすると、静止摩擦係数の理解がしやすいでしょう。 なお、静止摩擦係数は、上の例にはありませんが、1より大きい値となることもあります。 |
||||||||||||||||||||
| → 問題 へ |
||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||