|
|
|
|
|
| 水の豆知識 |
|
|
|
| VOL.1「渡航先の水事情」 2002.8 |
| 渡航先では生水は厳禁。あまり身近にあるのでつい日本と同じ様に扱ってしまいがちですが海外では気をつけましょう。水道水も必ずしも安心できません。殺菌が充分でなかったり、建物の老朽化で汚染されている場合もあるからです。また、日本の水は軟水ですがヨーロッパやアジアなどの多くは硬水なのでなれないと下痢を引き起こす場合があります。 |
| ◆ヨーロッパ◆ |
| ●水道水 |
| ほとんどの国で飲用可能。 |
| ●ミネラルウォーター |
| ヨーロッパなどのミネラルウォーターは通常「ペリエ」の様なガス(微炭酸)入りを指す。 |
| 日本と同じものが飲みたければ「ガスなし」を指示すると良い。エビアン、ボルヴィック |
| スコットランドや北欧の水道水は美味しいといわれるが、硬水で石灰分が多く体質に合わない人もいるので体調に自信がないときは飲まないほうが無難です。 |
| ◆アメリカ◆ |
| ●水道水 |
| 西海岸、東海岸とも主要都市では飲用可能。
但し、硬水なので胃腸の弱い人には合わない。 |
| ●ミネラルウォーター |
| どこでも簡単に購入できる。 |
| ◆中国・台湾◆ |
| ●水道水 |
| 中国では石灰分が多い硬水で飲用には不向き。お茶にして飲むのが普通です。
香港は比較的安全だが硬水なので避けた方が無難。台湾も飲用には不向き。 |
| ●ミネラルウォーター |
| 「鉱泉水」は600ml約3元 |
| ◆東南アジア◆ |
| ●水道水 |
| ベトナム、インド、バンコクでは生水は厳禁。水道水も飲用しない方が良い。屋台等の水は生水の恐れがあるので飲用は避けること。 |
| ●ミネラルウォーター |
| ホテルや空港で「エビアン」が入手可能。インドでは生水を入れて売っている場合があるのでキャップが開けられていないか充分チェックすること。東南アジアでは氷にも充分注意が必要。 |
| VOL.2「清涼飲料水は保存水」 2002.8 |
| 欧州で古くから知られているビルモント水は天然ガス入りのミネラルウォーターとしてドイツから輸出されていた。当時大変おいしいものだったらしく、特に肉中心の脂くどい食事をしているときの清涼感はすばらしかったという。炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ)を溶かした水にクエン酸や酢酸が加えられた。これは長らくソーダ水と呼ばれてきたものです。果汁や甘味料を添加したラムネやサイダーは日本ではなじみが深い。これを瓶詰にしたものは長期保存でき、遠くに運べる清涼飲料となった。 |
| VOL.3「浄水器」 2002.8 |
| 浄水器が家庭に入り始めたのは1964年東京オリンピックのころです。高度成長の波にのって産業が活性化し、都市部に人口が集中しはじめ水源が急激に汚れ始めたころなのです。当時は粒状活性炭のみで濾過するだけっだたので雑菌が繁殖し水と一緒に出てきてしまうという欠点がありました。現在では中空糸膜や高機能繊維を用いたフィルターなどがあり、それらを併用することにより理想に近い浄水器になったのではないでしょうか。 |
| 浄水器の売れ筋ランキング 注)東武百貨店2002年4月調べ。価格は店頭価格 |
| 商品名 |
メーカー |
価格 |
| ブリタフィヨルドメモ |
シービック |
6,500円 |
| ハイテクヘルスウォーターⅡ |
イメンス |
33,800円 |
| シーガルⅥ |
ゼネラルエコロジー |
80,000円 |
| 02クリンスイ |
三菱レイヨン |
9,800円 |
| トレビーノスーパータッチ |
東レ |
7,800円 |
| クリンスイスーパーSTX |
三菱レイヨン |
40,000円 |
| クリンスイスーパーピクシープロ |
三菱レイヨン |
9,000円 |
| クリンスイエミネント |
三菱レイヨン |
78,000円 |
| ハイパワークリンスイデミタイム |
三菱レイヨン |
6,800円 |
| トレビーノカセッティシグナル |
東レ |
7,500円 |
|
各メーカー浄水器を見る  |
| VOL.4「自然の浄化作用」 2002.9 |
| 自然浄化は細菌などの微生物の働きによるところが多い。水中には多種多様な細菌が住んでいてそれが有機物を分解する。たとえば川底の泥1g中に細菌が約10万個、カビが約1000個存在している。その数は川により、場所、時期などにより異なる。有機物が少ないうちは酸素を好む好気性細菌がそれを酸化分解する。最終的には水や二酸化炭素として放出される。有機物が逆に多すぎると、水に溶存している酸素が不足するために好気性細菌は酸化分解するための能力を失う。有機物の量は好気性細菌が分解するのに要する酸素量で表現されている。BOD
(生物化学的酸素供給量)である。これが溶存酸素量を超える様な大量の有機物が川に入り込むと、酸化分解が間に合わなくなるのは当然である。そこでは、酸素を必要としない嫌気性細菌が優勢となり、有機物は還元分解される。水は黒ずみ不快な臭いが生じる。そこで空気を積極的に送り込むと好気性細菌が勢いを取り戻す。これらの工夫は浄水場や多くの事業所で実施されているものである。細菌以外に藻類などが有機物などを取り込んで、無害な物質に変えていくのです。工場排水や生活排水からの汚染物質の中身は、有害な物質だけでない。食品事業所の中に排水溝の周辺に草が異常発生するという例があった。このようなところでは水の流れが妨げられたために嫌気性細菌が増殖し悪臭がたち込めていた。 |
| VOL.5「人間が出す汚染急増」 2002.10 |
| 都市化や工業化により生活や産業からくる汚水が大量に流される。人間の活動に伴う廃水は有機物やアンモニアなどを多く含み水中の溶存酸素量を大量に消費する。VOL.4でもふれた様に廃水は酸欠状態になり好気性微生物の活動が鈍くなる。よって嫌気性微生物が増えるため分解が非常に遅くなる。地球上では特定の地域に人間が集中しているので大量の生産と消費が都市部を中心に行なわれている。その結果プラスチック製品(環境ホルモン)や多種多様の汚染物質が廃水や廃棄物として大量に発生し大量に処分された。そのツケが水環境の異変、土壌汚染などの環境破壊につながっている。通常、飲料水は身近な川からとりこんでいる。その途中の過程で有害物質が多々混入されてしまう。微量でも生態系には少なからず異変をおこしている。有害物質を自然界に出さない努力をしなければならない。 |
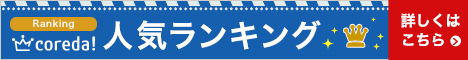
 |
| VOL.6「水」 2002.10 |
| 地球表面には15億立方キロメートルの水が存在している。形を変えながら地球上を循環している。気体・液体・固体の3相の形態である。これらの形態がたもたれているからこそ、今の地球の姿を可能にしている。酸素が大気組成比20%で安定していること、地表の平均気温が15℃であることも水によって育まれた生態系があるおかげなのです。水は全てにおいての源。生物は水に浸ったり、体内を水で満たすことで生命を維持している。優れたエネルギーの媒体の役目を果たしている。 |
| VOL.7「水の物性」 2002.10 |
| 水の物性は特異だ。凝固点0℃、沸点100℃、分子量18の物質としては異様に高い。表面張力もほかの液体よりはるかに大きい。分子同士を結びつける水素結合がこれらの物性をもたらしている。海水中には全ての元素が含まれているという。酸素やいろいろな栄養分も溶け込んでいる。 |
| VOL.8「庭は地球そのもの」京都と水 2002.11 |
| 多くの人は庭を好む。なぜ好むかというと心が癒されるから。庭にある自然、そこに輝く緑や咲く花を見るとき、その人の顔は和んでいます。そのような気持ちは人間に限らず、全ての動物に共通のものであります。もともと生命というもの自体、大地と水と空気によってうまれたものです。そこに母なる地球を感じるから心が癒されるのです。この「大地と水と空気」は「山と水と空」にも言い換えられます。「山と水」、即ち「山水」とは自然そのものであり地球そのものでもあります。「作庭記」に言う「生得の山水」また然り。それを京都に当てはめるとどうなるか。京都は三方を山に囲まれ、南に開けた土地です。即ち東山、北山、西山、川は北から南へ流れ、南の空は広く明るい。でも京都は決して水に恵まれた土地ではなかった。夏に水が枯れる事もしばしばあった。明治時代に琵琶湖疎水ができてようやく安定した水の供給が可能になりました。現在の東山の多くの庭園もそれがあって初めて作ることができたのです。代表的なものに枯山水という手法がありますがあれも水がなかったから比叡山から白川砂というのを採ってきて、水の流れをイメージしたものなのです。(船橋晴雄) |
| 京都の庭園ガイド |
| VOL.9「ミネラルウォーターの選び方」 2002.11 |
| 近年ミネラルウォーターの消費量が随分と伸びています。その要因として水がまずい、安全性に疑問という人たちが増えたことによるものでしょう。単にミネラルウォーターといってもその種類は結構あります。下記に分類分けをしてみました。 |
| 無処理水 |
| 加熱殺菌や濾過フィルターでの除菌処理などの減菌処理をしていないもの バルヴェール |
| 処理水 |
| ■除菌ウォーター |
| 濾過フィルターで除菌処理し加熱による減菌処理をしていないもの 六甲のおいしい水 |
| ■非加熱減菌ウォーター |
| オゾン減菌や紫外線減菌などの加熱ではない減菌処理をしたもの 龍泉洞など |
| ■加熱・殺菌ウォーター |
| 加熱処理で減菌したもの 大清水など |
| ■成分調整ウォーター |
| ミネラル成分調整、香料添加、電気分解などの処理をしたもの イオンウォーター |
|
| VOL.10「温泉」 2002.12 |
| 温泉とは25℃以上の地中から湧き出す温水・鉱水および水蒸気やその他のガスで温泉法に規定された遊離二酸化炭素、リチウムイオン、第一マンガンイオン、炭酸水素ナトリウムなど19種類の物質のうち1種類以上を含むものをいう。つまりさまざまなミネラルを含む温水の地下水ということ。温泉の医学的効果としては温熱・静水圧・浮力・粘性・化学成分などが作用し効果をもたらす。これに温泉地の自然環境、入浴の繰り返しにより反復刺激が加わり自律神経、内分泌系、免疫系などを介して体の諸機能を正常化し健康増進される。 |
| 温泉の分類 |
| 単純泉 |
含まれている成分濃度が薄い温泉。(日本の一般的温泉)無色・無臭・透明なものが多く、身体に対して刺激が少ない。効果は温泉によって異なる。 |
| 単純二酸化炭素泉 |
熱く沸かすと二酸化炭素が逃げてしまうため、34℃以下のぬるい温泉。炭酸ガスが抹消血管を拡張させるため入浴後もポカポカ。循環器疾患に効果がある。 |
| 炭酸水素塩泉 |
重曹泉 |
アルカリ性で皮脂や老廃物を洗い流すため肌がスベスベ。「美人泉」とよばれる。 |
| カルシウム・マグネシウム泉 |
鎮静作用があり、炎症をおさえる。 |
| 塩泉(食塩水) |
成分は海水とほぼ同じ。入浴後の保温効果が良い。 |
| 硫酸塩泉 |
ナトリウム硫酸塩泉 |
動脈硬化、高血圧に効果がある。 |
| カルシウム硫酸塩泉 |
鎮静効果がある。打身・ねんざ・切傷・火傷や動脈硬化に効果がある。 |
| マグネシウム硫酸塩泉 |
ナトリウム、カルシウム、にマグネシウムが加わった温泉。 |
| アルミニウム硫酸塩泉 |
皮膚や粘膜を引き締める。湿疹や真菌症などに効果がある。 |
| 含鉄泉 |
炭酸鉄泉 |
婦人病に効果がある。鉄イオンは酸化されやすく時間が経つとお湯に錆色の沈殿物ができる。(こうなると効果は半減) |
| 縁ばん泉 |
銅・コバルト・マンガンを多く含む。造血作用がある。 |
| 硫黄泉 |
玉子が腐ったようなという温泉。心臓の動脈を拡張させたり、解毒作用など効果の多い温泉。刺激が強いため高齢者、病弱、皮膚が弱い人には不向き。 |
| 酸性泉 |
酸性のため、湯が肌にしみる。皮膚が弱い人はただれに注意が必要。抗菌力があるので水虫に効果がある。 |
| 放射能泉 |
ラドン温泉。利尿作用があり、高尿酸血症や痛風、ガンに効果がある。 |
|
| 温泉ソムリエの温泉癒し温泉ガイド(温泉が学べる) 名湯100選(温泉療法医がすすめる温泉) |

 |
| VOL.11「水が病を癒す」 2002.12 |
| フランス南西部、ピレネー山脈北麓にルルドの泉がある。この泉の水を身体にかけたり、飲んだりすると不治とされている病気が治るという奇跡があると言われ、世界各地から数百万の人々がこの地を訪れます。水は最古から薬とされ欧州では古くからクリスマスや復活祭などの聖祭のときに汲む流水は病気を癒すといわれてきた。「○○の水を飲むと血液がサラサラし血圧が下がる」、「××の水を飲むと病気が治る」など理由をつけて水の効果を説くものがほとんどですが科学的に表現されていない場合が多い。ルルドの泉の場合、高濃度のゲルマニウムが多く含まれていることが最近になってわかりました。ゲルマニウムは鉄・マグネシウムなどと同じ元素の一つで人間の身体に必要なミネラルです。ゲルマニウムは鉱物に含まれる無機ゲルマニウムと漢方薬などに含まれる有機ゲルマニウムがあります。その効果は細胞内の電流バランスを整える作用があるようです。要するに血液がサラサラになり血行がよくなるということです。「××の水を飲んだら身体の調子が良くなった」と感じる人が多いようですが、ただ大量に水を飲む習慣がつき新陳代謝が活発になったことで改善されたのではないのでしょうか。現代において「ふつうの水」というものが大変入手が困難になっているのも事実です。でも身近なところに湧き水や伏流水など結構多くあるものです。 |
| 究極の名水100選 |
| VOL.12 「ヒートアイランド現象」 2003.2 |
| 大都市や工業地帯などでは、気候がその周辺等と比べ異なっている。このような地域では緑地が減り、建物や工場が隣接し道路や人が増え絶えず大量の熱を放出している。これがヒートアイランドと呼ばれる局地的な高温ゾーンを作り出している。その温度は3〜7℃も周辺に比べ高くなる。その原因は緑地が減ったため植物の葉からの蒸散量が減少したため大気が冷却しにくくなった。住宅が増えることにより道路も整備され地面は舗装・屋根化された。よって雨水が地中に浸透・拡散しにくくなり、地下水位が下がり表土が乾燥されやすくなったのが原因である。これは異常気象ではなく、ある部分だけが気候変動したものなのです。 |
 ヒートアイランド現象の実態解析と対策 ヒートアイランド現象の実態解析と対策 |
| VOL.13「有機物で汚れた水はどうなる」 2003.2 |
| 金魚を飼って楽しむ方はご存知でしょうがかわいいからとたっぷり餌をやろうと大量に餌を与えてしまうとたいていは何匹かは死んでしまいます。それは金魚の餌に含まれる主成分の有機物で水が汚濁されBODやCODが多くなり、水の中の溶存酸素が減少して窒息死するのです。きれいな水は無色透明ですが、それは多くの物を溶かし込む特性を持っています。魚はエラ蓋をパクパクさせることにより水をエラに送り込み、その水をエラで漉し分ける際に溶存酸素を分離して肺に送り込んでいるのです。魚が口を水面に上げてパクパクするようになったらそれは溶存酸素が少ないのです。溶存酸素は充分ばっきしていてもせいぜい1Lの水に7〜10mg(1mgは1gの1000分の1)程度しか溶けないので、水に砂糖などの酸素を奪いやすいものを混ぜるとたちまちにゼロになってしまいます。BODというのは生物化学的酸素要求量の略で水中の微生物のカロリーにあたる栄養物を測定したものです。人の栄養でも炭水化物や脂肪の様なカロリーなるものが大事で、それは胃や腸で消化し吸収され、それが血液に溶け込んで肺に達し、そこへ送られてきた酸素で「酸化」されそれで得たエネルギーで体温を保ったり、運動するための力になっています。バクテリヤなどの微生物も人間と同じ様にエネルギーを得ています。水中にBODがあると水が腐ってメタンガスや硫化水素が発生します。家庭下水のBODは200mg/Lですので、その下水1Lは30Lのきれいな水を溶存酸素0の汚れた水にしています。しかし川が流れたり、波立ったりしている間に長時間かかって水面から酸素を取り込みBODが分解して元の清浄な水に返ろうとしています。これを自浄作用といいます。 |
| VOL.14「水と調理法の関係」 2003.3 |
| フランス料理のポタージュやコンソメスープは油気の多い素材からアクを浮かせすくい取り得られるスープ。使用している水は硬水である。牛すね肉や挽肉、野菜などを鍋に入れ加熱する。水に含まれるカルシウムやマグネシウムは肉などの臭み成分と結合しアクとして取り除かれる働きをしているのです。日本の伝統的なものに吸い物がありますが、これ程味がそのままに素直に生かされているものはありません。ダシ取りはダシの素材と硬度の低い水が決め手になります。昆布からのグルタミン酸と鰹節からのイノシン酸が主体である。このように調理法一つでも水の硬度と密接に結びついているのです。 |
| VOL.15「進化する浄水器」 2003.4 |
| 浄水に加えて水質調整機能を備えた整水器なるものがでてきてる。鉛や重金属を除去するほか、料理や洗顔などの用途に応じた性質の水を手軽に作る事ができる。フィルターなどの寿命も長期化され面倒なフィルター交換を少なくする工夫も進んでいるようだ。アルカリイオン整水器と呼ばれ薬事法で医療用具としてさだめられている。水道水を浄化した後にカルシウムを添加し電気分解することでPH値の異なる酸性水とアルカリイオン水に分離させる。PH8.5の弱アルカリで整腸作用があり、PH9では緑茶の出が良くなったり、ご飯がふっくら炊ける。PHが低い酸性水は肌の引締めに効果があるとされ美容向けに使用できる。 |
| メーカー |
商品名 |
特長 |
価格 |
| 松下電器産業 |
PJ-A502 |
7種類のPH設定可能。大型液晶で画面が見やすい。 |
88,000円 |
| 松下電工 |
TK748-A |
重金属の鉛を除去するカートリッジを標準搭載。 |
45,000円 |
| TOTO |
TEK511 |
カートリッジを毎日自動的に加熱・洗浄。最長7年間交換が不要。 |
118,000円 |
|
各メーカーの整水器を見る  |
 |
| VOL.16「環境に優しく、用途無限の強酸性電解水」 2003.5 |
| 水に直流電流を流すと、両極にそれぞれ特長を持った水ができる。陰極側にアルカリ電解水、陽極側に酸性電解水が作られる。近年この酸性電解水が着目されている。強酸性電解水の殺菌効果は各分野で試みられた。医療分野では外傷、火傷、床ずれの処置、術後感染予防などに使われ始めた。また、アトピー性皮膚炎、胃潰瘍治療などにも効果を発揮することがわかってきた。食品分野ではO-157対策として期待された。効果が一過性のもので環境への負担が小さい。この酸性電解水を食品分野で実用化するためには電解という特定の条件で得られる次亜塩素酸水を食品添加物として認可されることが必要だった。2002年6月10日食品衛生法施行規則の一部が改正され次亜塩素酸水が食品添加物として認められた。なお次亜塩素酸水は最終食品の完成前に除去しなければならないとされています。 |
|
|
| VOL.17「活性酸素と水」 2003.6 |
| 「活性酸素」と健康の問題がクローズアップされている。活性酸素がガンや老化の引き金になっているという報告が次々とされている。活性酸素(スーパーオキシド)は呼吸によって取り入れられた酸素が体の隅々まで運ばれてエネルギーを生み出し生理作用として働く。その過程で生まれるのが活性酸素である。活性酸素は細胞膜など体内の不飽和脂肪酸と結合して有害物質である過酸化脂質を作るといわれており老化をはじめさまざまな成人病の危険度を高めてしまうとされている。この活性酸素を消去する酵素の一つに「SOD様物質」であり抗酸化物質として注目されている。このSOD様物質の能力を発揮させるのに水が大変重要なキーワードになっています。つまり水の状態によってSODの働きが大きく変化するのです。クラスターの小さい活性化されたミネラルを含んだPH7〜7.5のおいしい良い水だと活性酸素に十分対応できるのです。セラミックを利用することでこの水が半永久的に得られます。 |
|
|
| VOL.18「河川の水質現況」 2003.7 |
| 国土交通省では昭和33年から一級河川のおける水質調査を実施し、昭和47年から全国の一級河川の水質調査結果を取りまとめ公表している。平成13年度水質現況ではBOD平均値が最も良好だったのは尻別川(北海道)で3年連続の1位。最も悪かったのは綾瀬川(東京都・埼玉県)でした。(国土交通省) |
| 平成13年度全国河川ランキング |
| VOL.19「土壌の砂漠化・塩害」 2003.8 |
| 年間を通じて降水量が少ない地方では空気が乾燥しているため表層の土にわずかしかない水分が大気中に激しく蒸発する。そのため当然ながら地下水を汲み上げる。その地下水にはある程度の塩類が含まれていて、それが地表でどんどん濃縮されていく。少量の降水があっても、地下に浸透するだけの量はなく塩類はそのまま地表に残る。このような土地で農耕すると植物は根から地下水を吸い上げようとするが、通常植物はナトリウムイオンや塩素イオンなどは吸収せず土壌に残す。これを長年繰り返すことにより表土にどんどん蓄積される。ひとたび塩害が起こると土壌中の微生物や小動物がすめなくなり、植物は養分もとれず育たなくなる。土壌も痩せ植物・小動物を受け付けない最悪の世界を作り上げてしまう。砂漠化はこのようにして生まれ増えている。 |
| 砂漠化・土地荒廃問題に関するページ |
| VOL.20「雨水の利用」 2003.9 |
| 年間降水量が少ない国ではわずかな雨水でも貴重な水源であるために利用していますが、日本では年間降水量1700ミリメートルの大部分が利用されずに流されています。しかし最近になって水資源の有効利用という観点からみなおされ資源として活用しようという動きが活発化しています。都市部では各家庭や公共施設に雨水タンクを設置することにより雑用水を補ったり災害時の用水が確保できるなどのメリットがあります。雨水を利用するためには、降った雨を屋根から集水する、汚れや酸性が強い降り始めの雨水をカットする、貯留槽などに貯める、使用するところへ給水させる。集水機器、濾過フィルター、初期雨水カット雨樋、タンク等々の機器・装置が必要になります。この中で一番気をつけなければならないのは貯留槽で材質の成分の溶出がないもの(化学物質等)、藻の発生を防ぐために日光を遮断できるもの、蓋があり蒸発と埃や虫などの混入を防げるものでなくてはなりません。雨水タンクの設置に対して助成を行なっている自治体が多数ございます。 |
| 雨水利用機器 積水化学工業 タキロン |
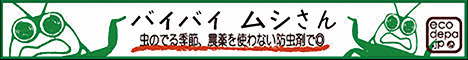 |
| VOL.21「有機性の廃棄物を資源に変える亜臨界水」 2003.11 |
| 水を使用し食品廃棄物や下水汚泥といった有機性の廃棄物を資源化させる研究がすすめられています。魚のアラからカルシウムやリンを取り出す、また廃棄木材から糖や油を抽出する。これが実現すれば廃棄物を資源としゴミの焼却場不足の問題も解消できる。まさに魔法の水なのです。亜臨界水とは水の温度と圧力を375℃、22Mpa(22気圧)まで上げると水でもない蒸気でもない均一流体になります。この点が臨界点で臨界点以上の状態を超臨界水と呼び、この水による反応を超臨界水反応と呼びます。また臨界点よりも温度・圧力が低い熱水を亜臨界水と呼び、この水による反応を水熱反応と呼びます。この水熱反応を利用し有機物の分子、例えばでんぷんやたんぱく質はそれぞれブドウ糖とアミノ酸に分解され低分子化されることにより固形物が液状化されます。亜臨界水を利用し簡単にしかも短時間の加水分解で食品廃棄物からたんぱく質などの有価物が得られるなど環境にやさしくとても安全な反応なのです。現在、産・学・官で実証実験が行なわれています、年内には最新鋭の処理装置が稼動する予定で注目を集めそうです。 |
| VOL.22「河川の水質現況」 2003.12 |
| 国土交通省では昭和33年から一級河川のおける水質調査を実施し、昭和47年から全国の一級河川の水質調査結果を取りまとめ公表している。平成14年度水質現況ではBOD平均値が最も良好だったのは尻別川(北海道)で4年連続の1位。最も悪かったのは鶴見川(関東)でした。(国土交通省) |
| 平成14年度全国河川ランキング |
| VOL.23「川の通信簿」 2003.12 |
| 国土交通省では、平成15年度全国の一級水系108水系において「川の通信簿」を実施しました。その結果、満点の5つ星評価の箇所が5地点、全箇所の平均は3つ星でした。この「川の通信簿」は市民や市民団体等と河川管理者が現地において共同して全国の河川空間の現状を評価するものです。これにより、河川空間の満足度を評価し、これを踏まえた河川整備・管理を図ります。(国土交通省) |
| 平成15年度川の通信簿ランキング |
| VOL.24「河川の水質現況」 2004.7 |
| 国土交通省では昭和33年から一級河川のおける水質調査を実施し、昭和47年から全国の一級河川の水質調査結果を取りまとめ公表している。平成15年度水質現況ではBOD平均値が最も良好だったのは後志利別川(北海道)で1位。最も悪かったのは大和川(近畿)でした。(国土交通省) |
| 平成15年度全国河川ランキング |
| VOL.25「水道水」 2004.8 |
| 戦後水道水は常に塩素で消毒されていることが義務づけられている。近年ではこの塩素に対する不満や塩素でも処理できない病原性微生物などが存在することにより大きく浄水施設が変わろうとしています。1996年6月埼玉県越生町で病原性微生物クリプトスポリジウムが水道水に混入し町民の7割近くが下痢や発熱といった被害にあった。元々クリプトは動物の胃や腸に寄生する原生動物の一種でありますが人間に感染することは比較的最近分かったことです。浄水場の上流の川を見て回っても特定できる原因が見当たらずどの様に浄水施設に混入したのかは今だ不明のままなのです。水道水の水は消毒してあり安心して飲める水だという水道水に不満や不安をもたれる様になってきました。カルキ臭が強い、発ガン性物質のトリハロメタンが含まれている、ビタミンCを破壊する、クリプトの混入が怖いなどです。塩素を入れる目的は消毒のため、原水中のさまざまな汚染物質を酸化分解させるのが目的です。戦後コレラ・チフス・赤痢など細菌による水系伝染病は克服されています。水道方施工規則で蛇口から出る水は0.1ppm以上の残留塩素が含まれていなければなりません。最近では0.5ppmから多い場合には2.5ppmにもなることがある様です。酸化分解剤として使われる塩素は河川の汚れと共に使用量が増えています。河川の汚染物質が増えるにしたがって凝集に使用される薬品量が増えているためです。水道水に対する不満や不安が増えることはあっても減ることはないのではないでしょうか。ではどのようにすれば塩素の注入量を減らせるのでしょうか。それは水源を汚さないことなのです。汚染の原因はほとんど人為的なものなのだからです。水源を汚さない様心掛けることが大切なのだと思います。 |
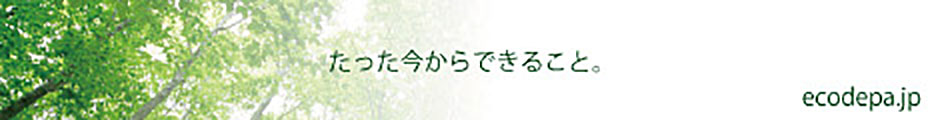 |
| VOL.26「奇跡の水、トラコテ」 2005.6 |
| トラコテはメキシコシティ北西のケレタロ州に位置し車で3時間程の小さな村です。この地方の井戸水を飲むと腰痛、糖尿病、アレルギー、アトピー、喘息、B型肝炎、癌、エイズなど、様々な病気に効くといわれています。水質を比べてみるとミネラル分がやや多く通常市販されているミネラルウォーターとなんら変わりはないのです。但し、1つ違うことは活性水素を多く含む天然水なのです。九大大学教授の白畑教授の実験結果ではフランスの「ルルドの泉」425ppt、メキシコの「トラコテの水」190ppt、ドイツの「ノルデナウの水」100pptと活性水素を多く含む天然水である事を突きとめました。呼吸で取り込まれる酸素の2%が活性酸素化するが、体内の坑酸化物質により分解される。ところがストレスや不健康な生活、環境の悪化などで現代人は過度の活性酸素を体内に抱え込んでいます。この様な背景から活性酸素を還元する活性水素水が注目を浴びることとなりました。 |
| まるごと飲む水素水 |
| VOL.27「川の水質現況」 2005.9 |
| 国土交通省では昭和33年から一級河川のおける水質調査を実施し、昭和47年から全国の一級河川の水質調査結果を取りまとめ公表している。平成16年度水質現況ではBOD平均値が最も良好だったのは尻別川(北海道)で1位。最も悪かったのは綾瀬川(利根川水系)でした。(国土交通省) |
| 平成16年度全国河川ランキング |
| VOL.28「川の水質現況」 2006.9 |
| 国土交通省では昭和33年から一級河川のおける水質調査を実施し、昭和47年から全国の一級河川の水質調査結果を取りまとめ公表している。平成17年度水質現況ではBOD平均値が最も良好だったのは尻別川(北海道)で1位。最も悪かったのは大和川(近畿)でした。(国土交通省) |
| 平成17年度全国河川ランキング |
| VOL.29「川の水質現況」 2007.9 |
| 国土交通省では昭和33年から一級河川のおける水質調査を実施し、昭和47年から全国の一級河川の水質調査結果を取りまとめ公表している。平成18年度水質現況ではBOD平均値が最も良好だったのは尻別川(北海道)で1位。最も悪かったのは大和川(近畿)でした。(国土交通省) |
| 平成18年度全国河川ランキング |
| VOL.30「軟水と硬水」 2008.1 |
| 硬度の低い水を軟水、硬度の高い水を硬水と呼びます。硬度とは水の中に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を言います。単位は一般的にアメリカ硬度ppmで表します。水1L中に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を炭酸カルシウムの濃度に換算した重量(mg:ミリグラム)です。日本の水道水の平均硬度は約60mg/lで軟水に分類されます。しかし国内でも水源の地形や地質によって溶け出す成分が違うため地下水を生活用水として使用している地域は硬度が高めなのです。千葉・茨城・東京・滋賀・福岡・熊本・沖縄などでは80mg/l以上の高硬度の地点もたくさん有ります。北海道・新潟・秋田・宮城・愛知・島根・鳥取などでは40mg/l以下の軟水です。この硬度とは生活にどの様な結びつきがあるのでしょう。水の硬度が高いと表2の様な症状がでます。硬水を軟化させる方法ですがイオン交換法(イオン交換樹脂)、アルカリ法(消石灰:水酸化カルシウム)のみ、または消石灰とソーダ灰(炭酸ナトリウム)を併用して硬度を除去する方法です。硬度成分は、炭酸カルシウムとして沈殿します。 |
| 水の硬度 |
|
|
|
水の硬度が与える影響 |
| 硬度 |
ppm |
| きわめて軟水 |
0〜40 |
| 軟水 |
40〜80 |
| やや軟水 |
80〜120 |
| やや硬水 |
120〜180 |
| 硬水 |
180〜300 |
| きわめて硬水 |
300以上 |
|
|
|
|
| ●せっけんカスが多く泡立ちが悪い |
| ●洗髪すると髪がギシギシする |
| ●入浴後手荒れや肌のかゆみがでる |
| ●洗濯物が黄ばみやすい |
| ●浴室床やバス底に白い模様がつく |
|
|
| VOL.31「ルルドの泉」 2011.12 |
| ルルドはフランスとスペインの国境でピレネー山脈の麓の小さな町。聖母マリアの出現とルルドの泉で知られカトリック教会の巡礼地になっています。19世紀、村の14歳の少女ベルナデッタが聖母マリアの導きで見つけたという湧き水がその後に多くの疾病患者を治癒をした水といわれることで有名です。ルルドの泉はピレネー山脈の石灰層を通過した水で、カルシウム含有量の多い、いわゆる硬水です。カルシウム含有量の多い「硬水」を飲んでいると脳梗塞や心筋梗塞が予防できるというのは医学的に確認されています。ルルドの泉の成分はPH:8.5、ORP:133、カルシウム:50ppm、マグネシウム:5〜10ppm、硬度:130〜170です。ルルドの泉はアルカリ性で石灰岩質の自然なろ過でカルシウムやマグネシウムを適度に含んだ水ということになります。 |
|
 ヒートアイランド現象の実態解析と対策
ヒートアイランド現象の実態解析と対策