熱と温度(2) |
|
私たちが日常使っている温度の単位は、1気圧のもとで水が凍る温度を0℃、水が沸騰する温度を100℃として、温度計でその間を100等分した温度差を1℃とするものです。この温度をセルシウス温度といいます。 これは、世界最初の実用的温度計を提唱したスウェーデンの天文学者・測地学者であるアンデルス・セルシウス(1701〜1744)に由来するものです。セルシウス温度の単位はセルシウス度、または、単に度を用います。記号は℃です。 物体を構成する原子や分子の熱運動は、温度が高くなるほど激しくなります。 したがって、温度は、熱運動の激しさを表す量と考えることができます。 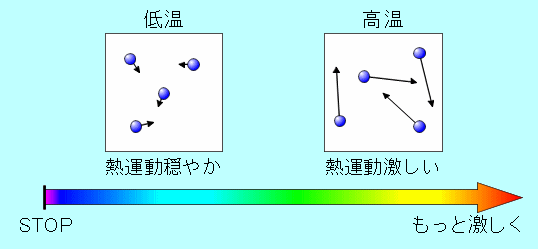 温度が高くなる方を考えると、原子や分子の熱運動がどんどん激しく(速く)なっていけば、温度がどんどん高くなることになります。例えば太陽の中心部の温度は、約1600万度なのだそうです。「あちちっ」なんてもんじゃないですよね。 一方、温度が低くなる方を考えると、熱運動がだんだん穏やかになって、速さが0になってしまうと、それ以上穏やかな運動はできません。 したがって、温度には、下限があるということができます。 温度が低くなっていって、分子や原子の熱運動が止まってしまう温度、それは、−273℃(厳密には−273.15℃)なのです。 地球上はもちろん、宇宙のどこを探しても、温度が−500℃だとか−1000℃だとか、そんな温度は存在しないのです。 日常生活で使うには、セルシウス温度(℃)が便利なのですが、温度(熱運動の激しさ)が、−273℃が下限でそこで熱運動が止まってしまうことから、科学的には、この温度を0として、目盛りの間隔をセルシウス温度と同じにした温度が定められています。これを絶対温度といい、絶対温度の単位は、ケルビンが用いられます。記号はKです。−273℃=0Kです。 なお、絶対温度の単位であるケルビンは、イギリスの物理学者で、絶対温度目盛りの必要性を説いたケルビン卿ウィリアム・トムソンに由来します。 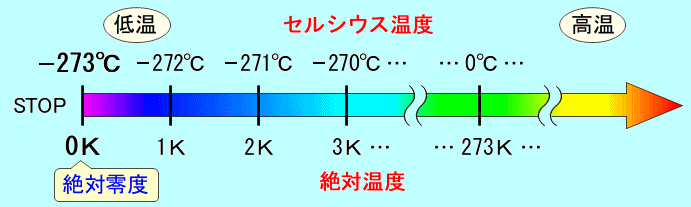 (1) ( )℃=0K (2) 0℃=( )K (3) 27℃=( )K (4) 100℃=( )K (5) 温度差 1℃=温度差( )K |
||
| → 答え合わせ へ |
||
| |
||