みんなで音の速さをはかろう |
|
空気中を音が伝わっていく様子をビデオのスロー再生で視覚的にイメージできるようにします。屋外で、みんなで実験に参加できます。ビデオのコマ数から音の速さも測ることができます。また、光の速さが、音と違いとても速いことも確かめられます。
使用する用具は次のものです。 旗(横断歩道にある物くらいの大きさ)20本、巻き尺、陸上のスターターピストル、ビデオカメラ、テレビ、(ビデオデッキ)、スピードライト
| [実験] (1) 100mの直線上に、20名ほどがほぼ等間隔に旗を持って並びます。下図のように、直線の一端にスターターピストルを持った人が立ち音源となります。旗を持った人は音源と反対の方を向き、旗を下げて待ちます。音源と反対の方には、ビデオカメラを持った人が立ちます。 (2) ピストルを持った人の「ヨーイ」の声と共に、旗を持った人は精神を集中します。ピストルの「パーン」という音が聞こえたら、即座に旗を上げます。この様子を、ビデオカメラで撮影します。これを、2〜3回繰り返します。 (3) ピストルを持った人は、ピストルをスピードライトに持ち替え光源となります。旗を持った人は光源の方を向き、上と同様に光が見えたら旗を上げます。 (4) ビデオの1秒間のコマ数を確認するため、デジタル時計(秒標示のあるもの)を撮影しておきます。 |
|
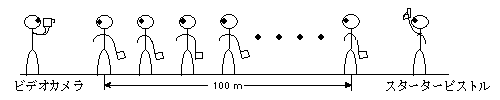 |
| [観察] (1) デジタル時計の映像をコマ送りし、ビデオの映像が1秒間に30コマであることを確認します。 |
 ↑時計を撮影し、毎秒30コマを確認 |
| (2) 撮影したビデオをみんなで見ます。スロー再生すると、音が音源からしだいに伝わっていく様子がよくわかります。 (3) コマ送りで、音源に一番近い人が旗を上げてから一番遠い人が旗を上げるまでのコマ数を数えます。ビデオの映像は1秒間に30コマですから、数えたコマ数から、音が100mを伝わる時間がわかります。この値から音の速さのおおよその値を求めることができます。 [音の速さの測定] 音が100m伝わるビデオのコマ数は9コマです。よって、時間は9/30=0.3秒、音の速さは100/0.3≒330m/sとなります。 |
 ↑一番奥の旗が肩の横 |
 ↑手前の旗が肩の横 |
|
| (4) 光については、同時に旗が上がることから、音と違ってとても速いことがわかります。 |
 ↑光では同時に旗が上がる |
| [留意点] (1) ビデオ撮影は、列の横から撮ると一人一人の大きさが小さくなり、旗の判定も難しくなります。よって、右図のように、列を縦に、遠方が小さくならないように望遠で撮ります。 (2) 観察(3)で旗のどの位置でコマ数を数えるかについては、肩の横、旗が水平になった位置が一番数えやすいです。 |
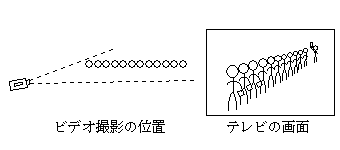 |
| [光の速さの測定例] 上の実験では光の速さは測れませんが、次の方法で測ることができます。NHKのテレビ放送で、午後7時のニュースなど通常の放送と衛星放送で同じ番組をやっている時間があります。2台のテレビを用意し、それぞれの方法で受信して画面を比べると、衛星放送の方がわずかに遅れていることがわかります。ビデオカメラでこの2台のテレビを1つの画面に撮影し、ビデオのコマ数から通常の放送と衛星放送とのずれの時間を測ります。ずれを7.5コマ、日本と放送衛星との距離を37400kmとすると、光(電波)の速さは 3.0×108m/sとなります。 |
 ↑左が衛星放送で、少し遅れている |
 ↑左の画面が上から変わるところ |
| [備考] ・[光の速さの測定例]については、岩下紀久雄 氏.”VTRの「コマ送り再生」機能を利用した物理実験”.昭和60年度東レ理科教育賞受賞作品集.財団法人東レ科学振興会,1986,p.5-7. を参考にしました。 ・私はこの実験を昭和62年に初めて行ってみました。上に使った写真は平成元年に撮影したものです。生徒は前任校の生徒で、今から見るとスカートがずいぶん長いですね。もちろん、ごく普通の生徒たちです。 |
以上は、平成5年に「視聴覚機器を使った物理実験」として書いたものの一部を簡略に記したものです。
宮田 佳則 (新潟高校)